
日本で消費税が導入されたのは平成元年4月1日です。
実は、消費税が導入される前までは、その前身として「物品税」という税金が存在していました。
今回は、消費税の前身である「物品税」とはどんな税金なのかについて、その歴史とともに解説したいと思います。
物品税と消費税の違い
今現在、日々の生活の中に浸透している消費税は、我々消費者にとって最も身近な税金のひとつであるといえます。
消費税は、事業者以外が行う取引などの課税対象外となる取引や、土地や有価証券の譲渡、社会保険医療、教育費などの非課税とされる取引を除き、基本的にはすべての品目を対象に課税されます。
令和元年(2020年)から軽減税率制度がスタートし、お酒や外食を除く飲食料品の譲渡、一定の定期購読の新聞には軽減税率8%が適用されることとなりました。
一方、消費税が創設される前に存在していた「物品税」は、すべての品目に対して課税されるのではなく、奢侈品(しゃしひん)や嗜好品(しこうひん)、つまり生活必需品以外の「ぜいたく品」に対してのみ課税されていました。
つまり、消費税と物品税の違いは、課税の対象範囲の違いにあります。
物品税の草案は明治初期に創設されるも施行されず
徳川幕府が大政奉還を行い、明治の世となった当初から、実は物品税の導入が検討されていました。
明治6年(1873)、明治政府は地租改正事業を開始し、それまで税率や税負担などがまちまちであった年貢制度を改めて、全国公平画一の土地税制を創設するとともに、安定した税源を確保しようとしました。
地租改正条例で、明治政府は、近世とは異なり作物の豊凶などにより地租は増税も減税もしないことを宣言し、その税率については、地租の税率は地価の3%とするが、今後「物品税」が整備され歳入が増加した際には、地価の1%まで地租を減税する方針を示しました。
当時の政府は、「茶」や「煙草」、「材木」を将来有望な課税物品であると捉えて物品税の導入を検討していました。
しかし、当時のアメリカではコーヒーの代用品として緑茶が飲用されており、日本にとって茶は生糸とともに明治日本の重要な輸出商品の一つであったため、勧業奨励に重点が置かれるようになり「物品税」は課税されませんでした。
また、材木についても物品税の課税は断念され、煙草については明治8年に煙草税則が公布され、「煙草税」として物品税とは別に施行されることになりました。
物品税誕生前に制定された主な個別消費税
物品税が制定される前に制定された個別消費税には「煙草税(専売局益金)」「酒税」「砂糖消費税」「織物消費税」「石油消費税」があります。
これらの税目が制定された背景は、やはり日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦などの戦争体制の強化、戦費の調達のためというのが理由としては大きいです。
また、間接税の増税は国民の購買力の吸収と消費の節約を図るという経済政策を実現する手段でもありました。
一方で、増税にあたっては奢侈的消費に対する高率課税や不要不急消費への課税も重視して、国民の負担能力や生活上の必要性に一定程度の配慮もされていました。
北支事件特別税・支那事変特別税の一つとして「物品特別税」が制定される
昭和12年(1937年)に、中華民国北京(北平)西南方向の盧溝橋で起きた日本軍と中国国民革命軍第二十九軍との衝突事件(盧溝橋事件)の発生により日中間の緊張が一気に高まり、日中戦争へと突入していきました。
日本では、紛争が勃発した当初は「北支事件」と呼ばれており、戦費を調達するために創設された北支事件特別税が創設されました。
このうちの一つに「物品特別税」という税目があり、これが後の「物品税」の前身となる税金です。
物品特別税の物品は2種に分かれており、第一種にはダイヤモンド、ルビー、水晶、真珠のような貴石、半貴石を用いられて製された製品、金、銀、白金のような貴金属製品または貴金属を用いられた製品、鼈甲製品、珊瑚製品などがあります。
第二種には、は写真機、写真引伸機、映写機およびその部分品、付属品、写真用乾板、フィルム、感光紙、蓄音機およびその部分品、レコード、楽器およびその部分品があります。
第一種は小売業者から消費者に売られる時、第二種は製造場から引き取る時に課税され、税率は両種ともに20%であり、取引価格に対して課税されていました。
なお、これらの物品の輸入品にも同様に課税されていました。
昭和13年(1938年)には支那事変特別税に移行し、第一種の甲類・乙類、第二種の甲類・乙類、第三種に区分されるようになります。
第一種は北支事件特別税と同様の品目が課税対象とされ、新たに乙類として時計や繊維関連の製品(メリヤスやレース、フェルト及び同製品)が課税対象となり、税率は甲類が15%、乙類が10%とされました。
第二種の甲類は北支事件特別税と同様の品目の他「双眼鏡、銃及びその部分品」新たに課税対象とされ、新たに乙類として「ラジオ、扇風機、暖房用ガス・電気・石油ストーブ」などが課税対象とされ、税率は甲類が15%、乙類が10%とされました。
第三種はマッチや飴・アルコール飲料が課税対象とされ、マッチは1000本につき5銭、みりんや焼酎・ビールは一石につき5円、ぶどう酒は一石につき10円、その他の種類は一石につき7円と個別に税額が規定されていました。
1940年「物品税法」が恒久法として制定され「物品税」が誕生
上述の支那事変特別税は昭和15年(1940年)までの時限立法による特別税でしたが、戦況は泥沼化しさらに戦費が必要となったため、昭和15年(1940年)に「物品税法」が恒久法として制定され、今の消費税の前身となる「物品税」が誕生することとなりました。
課税対象品目や区分、税率は支那事変特別税の物品特別税の頃のものそのままを引き継ぎました。
太平洋戦争に突入した年でもある昭和16年(1941年)には、第一種の丙類・丁類として靴、事務用器具が、第二種の丙類・丁類として紙、セロファン、電球類、ミシン、板ガラスなどが追加され、税率も甲類50%、乙類20%、丁類10%と大幅に引き上げられました。
その後、昭和18年(1943年)には税率が甲類80%、丁類30%に引き上げられ、終戦間際の昭和19年(1944年)にはなんと甲類120%、乙類60%、丁類40%というとてつもない高率にまで引き上げられました。当時の戦局がいかに厳しかったかがうかがえます。
物品税は戦時経済体制のもとで「奢侈的消費の抑制」を名目に導入されましたが、宝石や毛皮などの高級品・ぜいたく品の消費税高は本来的に大きなものではなく、戦費調達の必要性が増すにつれて物品税は国民への生活用品への課税・増税となり、課税対象外の物品も結局は原価に転嫁されるため、生活に必要なあらゆる商品の物価が高騰し、実質的にはお金持ちではなく一般大衆にとっての重い負担となっていたのです。
奢侈品や高級品などに対する課税だけでは、当初予定していたほどの税収が得られなくなってしまったため、次第に課税対象が一般大衆の生活必需品にまで拡大され、実質的には「大衆課税」となってしまい国民の生活を苦しめるものとなってしまいました。
戦後はシャウプ税制により直接税を中心とした税体系に
アメリカの影響下にあった第二次世界大戦後、所得税をはじめとする法人税・相続税といった直接税を中心とする恒久的・安定的な税体系を目指すシャウプ勧告に基づいた税制が昭和25年(1950年)に施行され、現在の日本の税制の基礎となりました。
物品税の戦時下のとてつもない高率の税率は、各業界からの陳情を受けて徐々に引き下げられていきました。
また、1950年11月30日に政府が提出した物品税改正法案では、それまで課税されてきた万年筆、シャープペンシル、ミシン、アイロン、安全カミソリ、板ガラス、滋養強壮剤、懐中電灯、提灯、すだれ、扇子、団扇、カレンダー、紅茶、ヒキ茶、実物投影機(エピスコープ、書画カメラ)、絵葉書、広告用幟、蜂蜜は無税とされることとなりました。
戦後の物品税は、戦時中と比べて課税対象品目が縮小され、税率も低くなったため、低所得者でも購入せざるをえない食料品等の生活必需品などが課税対象外で、代わりに高所得者が購入する贅沢品には高い税率で課税されるという仕組みが、超過累進課税の所得税の税制と相まって一億総中流社会の原動力になったともいえます。
しかし、昭和40年代には、戦後の高度経済成長が終焉を迎え、ニクソンショック(ドルの金兌換停止発表)や中東戦争を契機とするオイルショックなどの影響により不況となり、昭和50年代には不況による歳入欠陥に起因した財政危機を打開するために、国民に広く薄く負担を求める一般消費税の導入が議論されましたが、結局実現には至らず、課題として残されることとなりました。
そして、昭和62~63年(1987~1988年)にかけての抜本的税制改革では、高齢化、国際化などの経済社会の構造変化にあわせ、所得・消費・資産等の間でバランスのとれた税体系の構築が目指されるようになり、再び一般消費税の導入の議論に拍車がかかるようになりました。
消費税の創設が叫ばれるようになった理由として特に大きいものは、高齢化社会への対応という問題がありました。
日本は昭和63年当時でもすでに世界の主要国においても例をみない早さで人口の高齢化が進んでおり、年金、医療、福祉のための社会保障費の財源確保が喫緊の課題となっていました。
それまでの、現役世代の働き手の所得(給与所得等)に対する課税に頼った税制では、働き手の重税感や不公平感が高まり、事業意欲や勤労意欲をも阻害することにもなりかねないことが懸念されました。
こうした社会問題に対する懸念が追い風となり、昭和63年(1988年)12月30日に「消費税法」が施行され、平成元年(1989年)4月1日から、国民に広く薄く負担を求める「消費税」が導入されることとなりました。
また、これに伴い「物品税」は廃止されることとなりました。
なぜ物品税は廃止されたのか
なぜ物品税は廃止されることになったのでしょうか?
これにはいくつか理由がありますが、主な理由を3つ紹介します。
商品やサービスの多様化に対応できないから
物品税は課税対象の品目を予めリストアップしておく必要がありますが、社会の複雑化や技術の発展によりそれまでに存在しなかった新しい商品やサービスが次々と生まれてくるような状況で、課税対象物品を規定するのは困難です。
昭和終期にはコンピューター製品などの今まで存在しなかった商品が急速に出回るようになり、昭和59年の税制改正では急いで電子製品も課税対象品目として拡大する税制改正が行われました。
このように、新商品の登場に合わせてその都度物品税の課税対象範囲の拡大をしているようでは立法手続きの面で問題があり、業界からの反発は必至で不公平感を生みます。
それに対し、消費税は「事業者が国内において対価を得て行う資産の譲渡等」に課税されるため、課税対象の品目を予めリストアップする必要がなく今まで存在しなかった新しい商品やサービスに対しても課税することができます。
サービスに対して課税されないから
物品税は、その名のとおりあくまでも「物品」に対して課税される税金なので、原則としてサービスに対しては課税されませんでした。
産業構造としてサービス業の割合が高くなってきている中、サービス業に対して課税できないのでは税収の確保が難しくなってしまいます。
それに対し、消費税の課税対象は「資産の譲渡等(資産の譲渡・貸付け、役務の提供)」とされているため、サービスに対しても課税されます。
生活必需品か贅沢品かの判定が困難だから
物品税は、生活必需品か贅沢品かの線引きが困難であるという問題点があります。
例えば、物品税法上、レコードは課税対象とされていましたが、童謡を収録したレコードは教育的観点から非課税とされていました。
そのため、皆川おさむの「黒ネコのタンゴ」、子門真人の「およげ!たいやきくん」などのレコードについて、課税対象か否かの議論が行われたことがあります。
「およげ!たいやきくん」は童謡と判定され非課税とされましたが、「黒ネコのタンゴ」は東京国税局以外の管内では歌謡曲とみなされ課税されるという事態となりました。
税理士や国税局職員、裁判官などが「およげ!たいやきくん」が童謡か歌謡曲かを一生懸命聴いて判定している姿は想像しただけでも不毛ですし、その時間をもっと他のことに使った方が社会全体にとって有用だと思います。
この他にも、類似製品であるものの課税・非課税かの判断が課税庁により異なるという問題が相次ぎました。
また、生活必需品か贅沢品かは、その時代の価値観や流通量、需給バランス、価格などによって移ろい変わっていくものであるため、一律に生活必需品か贅沢品かの線引きをすることは非常に困難です。
今後「物品税」が復活することがあるか?
今後、「物品税」が再び施行されることはあるのでしょうか?
この点については、僕自身の見解となりますが、物品税が復活することは十中八九ないと思います。
物品税には上述のような問題点がありますが、消費税は物品税の問題点を全てカバーしているため、今の消費税が物品税に取って代わられることはまずないでしょう。
今後、消費税率は15%、20%と引き上げられる可能性はありますが、生活必需品への配慮は軽減税率対象品目の拡大により行われると思います。
物品税のように「特定の品目だけ課税する」と規定するよりも、今の消費税のように「原則すべての品目に課税するけど、特定の品目だけ非課税または軽減税率とする」と規定するほうが立法手続きの面でも課税の公平性の面でも優れているため、消費税を廃止して物品税を復活させるメリットはありません。
今後、ゴルフ場利用税や入湯税のような個別消費税が新しく導入されることはあり得るかもしれませんが、物品税が復活することはおそらくないでしょう。
まとめ
物品税は昭和の戦時体制下で生まれ、太平洋戦争終盤にかけて信じられないほどの高税率に引き上げられました。
贅沢品に課税するという名目でありながら、実質的には「大衆課税」となり戦時下の国民の生活を苦しめるものとなってしまいました。
戦後は、シャウプ勧告に基づき所得税をはじめとする直接税を中心とする税体系が構築され、物品税は徐々にその存在感を薄めていきました。
しかし、不況のあおりや少子高齢化への対応が喫緊の課題となり、国民に広く薄く負担を求める一般消費税の導入が叫ばれるようになったため、昭和63年(1988年)の消費税法の制定に伴い、物品税は廃止されることとなりました。
物品税には課税の公平上の問題点も多いため、おそらく今後復活することはないと思われます。


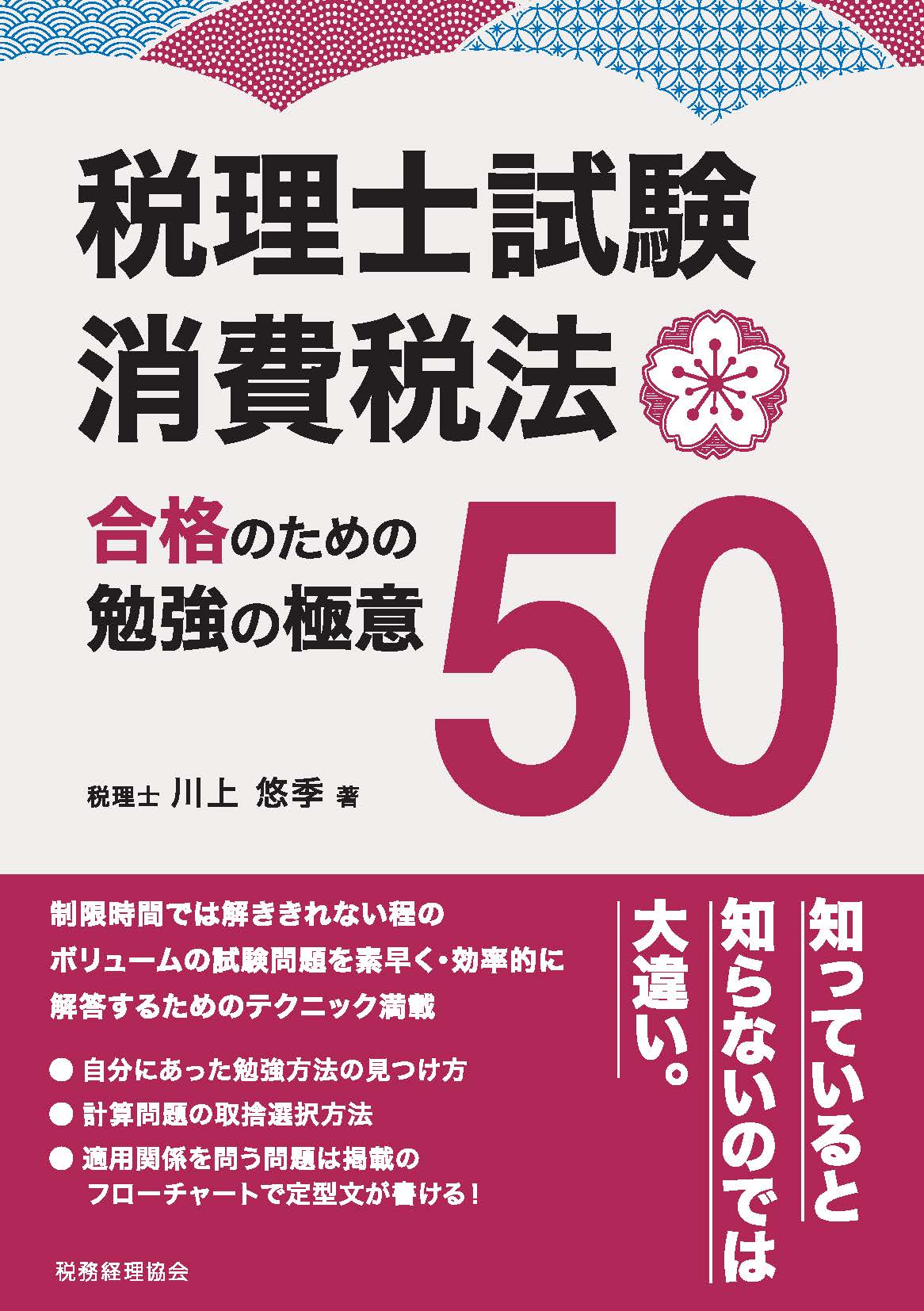











-端っこカット小-1.jpg)
はじっこカット小-1.jpg)
-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)
-端っこカット小.jpg)
はじっこカット.jpg)
-はじっこカット小.jpg)


