
以前書いた記事↓では、不動産等の地代家賃に関する収益の計上時期について解説しました。
この不動産等の地代家賃に係る収益計上時期について、巷では「個人事業者と法人とでは取扱いが異なる」という言説があるようですが、果たしてこれは本当なのでしょうか?
今回は、不動産等の地代家賃に係る収益計上時期に係る個人事業者と法人の取扱いについて考察したいと思います。
個人事業者と法人とで異なるとされている取扱いとは
不動産などの資産を賃貸借している場合の賃貸借料の収益計上時期については、次の2通りの方法があります。
② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法
この2種類の方法について、「個人事業者は①、②いずれでもOK、法人は②しかダメ」という言説が一部流れているようですが、これは本当に正しいのでしょうか?
以下、この取扱いの差異について詳しく検討していきたいと思います。
法人 → ②しかダメ
個人事業者が①も②もOKな根拠
個人事業者が、「① 契約上の支払日に計上する方法」「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」のいずれも採用してOKとする根拠として、国税庁が公表している法令解釈通達『不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について』において、次のような記載があります。
直所 2-78
昭和48年11月6日国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について
所得税法第26条第1項《不動産所得》に規定する不動産等の賃貸料の収入金額の計上時期に関する取扱いを下記のとおり定めたから、これによられたい。(理由)
不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認めることとしたものである。記
(不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合)
1 所得税法第26条第1項に規定する不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、所得税基本通達36-5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》により、原則としてその貸付けにかかる契約に定められている賃貸料の支払日の属する年分の総収入金額に算入するのであるが、その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっている場合で、次のいずれにも該当するときは、同法第67条の2《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける場合を除き、その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とすることができる。(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。
(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること
(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。
(注) 「不動産等の賃貸料」には、不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金、権利金、名義書替料、更新料、礼金等は含まれない。(不動産等の貸付けが事業として行なわれていない場合)
2 その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記1の(1)に該当し、かつ、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記1の(2)に該当するときは、所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額については、上記1の取扱いによることができる。(計上時期の変更のあつた年分の総収入金額の計算)
3 その賃貸料にかかる収入金額につき賃貸料の支払日により総収入金額を計算していた者が新たに上記1もしくは2の取扱いによることとした場合または上記1もしくは2の取扱いにより総収入金額を計算することとしていた者が賃貸料の支払日によることとなつた場合には、次による。(1) 新たに上記1または2の取扱いによることとした年分の前年以前の貸付期間にかかる賃貸料の額のうち、支払日が到来していないため当該前年以前の各年分の総収入金額に算入されていない金額がある場合には、その金額は、新たに上記1または2の取扱いによることとした年分の総収入金額に算入する。
(注) 前払の賃貸料については、たとえば前月払の月額賃貸料の場合には、新たに上記1または2の取扱いによることとした年分は、11か月分の賃貸料を総収入金額に算入する。
(2) 上記1または2の取扱いによらないこととなつた最初の年分の前年以前に支払日が到来している賃貸料の額のうち、その賃貸料にかかる貸付期間が経過していないため、当該前年以前の各年分の総収入金額に算入されていない金額がある場合には、その金額は、当該最初の年分の総収入金額に算入する。(経過的取扱い)
4 この取扱いは、今後処理するものから適用する。この場合において、昭和47年分以前の所得税については、その年分の賃貸料にかかる前受収益および未収収益についての明細書を提出したときは、上記1の(2)および(3)の要件を具備しているものとして取り扱うものとする。
上記のとおり、所得税法上は、事業的規模であるか否かにより若干の違いはあるものの、「① 契約上の支払日に計上する方法」「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」のいずれの方法も認められることが明記されています。
この個人事業者の取扱いについては特に異論はないようです。
法人が②しかダメと言われるようになった理由
法人の場合は、「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」しか認められず、「① 契約上の支払日に計上する方法」は採用できないと言われることがあります。
一体なぜ、このような言説が広まったのでしょうか?
まず、法人税法第22条の2第1~2項において、益金の額の算入時期について次のように規定されています。
第二十二条の二 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
法人税法上の益金の額の算入時期について定めた法人税法基本通達2-1-29において、以下のような記載があります。
(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)
2-1-29 資産の賃貸借(金融商品(平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。)に係る取引、法第64条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引及び2-3-62《暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額》の対象となる取引に該当するものを除く。以下この章において同じ。)は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は2-1-21の2の事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)について、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日において収益計上を行っている場合には、その支払を受けるべき日は、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」により改正)(注)
1 当該賃貸借契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまで当該使用料等の額を益金の額に算入することを見合わせることができるものとする。
2 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には(注)1の取扱いによらないのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。
3 収入する金額が期間のみに応じて定まっている資産の賃貸借に係る収益の額の算定に要する2-1-21の6の進捗度の見積りに使用されるのに適切な指標は、通常は経過期間となるため、その収益は毎事業年度定額で益金の額に算入されることになる。
上記太字・下線部分で示したとおり、「契約上の支払日」が、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に「近接する日」に該当するか否かの解釈がポイントとなります。
ここで、「資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)」のカッコ書き(前受けに係る額を除く。)の部分の解釈が最大のポイントとなります。
このカッコ書き(前受けに係る額を除く。)の捉え方には次の2パターンが考えられます。
Ⓑ 「前受け」を経理処理の方法として捉える考え方
『Ⓐ 「前受け」を時期的な意味で捉える考え方』によって解釈した場合は、「契約又は慣習によりその支払を受けるべき日」が実際の不動産等の貸付期間よりも時期的に前である場合(翌月分の家賃を当月に収受した場合など)は、上記通達の下線部分の取扱いはない(=支払日に益金算入しちゃダメ)ということになります。
一方、『Ⓑ 「前受け」を経理処理の方法として捉える考え方』によって解釈した場合は、支払日に収受した使用料等の額を経理上「前受収益」などの経過勘定で処理した場合は益金算入されないということになります。これは、逆に言えば、支払日に収受した使用料等の額を「前受収益」などの経過勘定でなく「受取家賃」などの収益勘定で経理処理した場合は、それは「前受けに係る額」ではないため、益金算入して良いということになります。
巷では、上記Ⓐの考え方を根拠に、法人は「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」しか認められず、「① 契約上の支払日に計上する方法」は採用できないという言説が広がっているようですが、それは本当に正しいのでしょうか?
国税庁の法令解釈通達で①もOKと明記されていた
実は、国税庁が公表している法令解釈通達『【改正】(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期) 』おいて、法人であっても「① 契約上の支払日に計上する方法」を採用することができる旨が明記されていました。
【解説】
1 本通達は、賃貸借契約に基づく使用料等の収益の帰属時期について、原則として履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し期間の経過に応じて益金の額に算入することになるが、例外的にその支払を受けるべき日又は係争が解決し支払を受けることとなる日の属する事業年度の益金の額に算入することも認める旧通達2-1-29《賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期》の取扱いについて平成 30 年度税制改正後も同様となる旨を明らかにするものである。
このように、使用料等を支払日の属する事業年度に益金算入することが認められると明記されているため、法人の場合は「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」しか認められず、「① 契約上の支払日に計上する方法」は採用できないとする考え方は誤りであることがわかりました。
基本通達内のカッコ書き(前受けに係る額を除く。)の捉え方も『Ⓑ 「前受け」を経理処理の方法として捉える考え方』によって解釈するのが正しいということになります。
よって、個人事業者であっても法人であっても「① 契約上の支払日に計上する方法」「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」のいずれも採用してOKということがわかりました。
そもそも、不動産等の賃貸という同一の取引について、個人事業者の場合は支払日に収益計上が認められるのに、法人の場合は支払日に収益計上は認められないというのは、課税の公平の観点からもおかしな話なので、当たり前っちゃ当たり前のことだと思います。
(参考)平成30年度税制改正で何が変わったのか
平成30年3月30日に収益認識に関する包括的な会計基準となる企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が公表され、これに伴い平成30年度税制改正において法人税法上の取扱いも「収益認識に関する会計基準」に準拠した内容に改正されました。
従来まで、賃貸借契約に基づく使用料等の収益の帰属時期については、法人税法上も所得税法上も「① 契約上の支払日に計上する方法」が原則、「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」が例外という位置づけになっていました。
しかし、賃貸借契約に基づく使用料等は「収益認識に関する会計基準」に規定する「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」に該当することを踏まえ、平成30年度税制改正において、法人税法上は「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」が原則、「① 契約上の支払日に計上する方法」が例外という位置づけに変わりました。(ちなみに、所得税法上は現在も①が原則、②が例外という位置づけです。)
原則と例外の位置づけが逆転しただけで、「① 契約上の支払日に計上する方法」が禁止されたわけではないため、今後も「① 契約上の支払日に計上する方法」は認められることになります。
消費税法上の資産の譲渡等の時期も同様
消費税法では、不動産等の賃貸借について、そもそも貸主が個人事業者であるか法人であるかの別は規定されていません。
消費税法における資産の譲渡等の時期を「契約上の支払日」とする方法の根拠は、消費税法基本通達9-1-20において次のように規定されています。
(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)
9-1-20 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。(後略)
ただし、賃貸料を「前受収益」などの経過勘定で処理している場合は、消費税法基本通達9-1-27により、資産の譲渡等の時期を実際の貸付期間に対応させることになります。
(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-27 資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受ける事業者を除き、現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。
つまり、消費税法上も、不動産等の貸主が個人事業者であるか法人であるかは関係なく、資産の譲渡等の時期については「① 契約上の支払日に計上する方法」「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」のいずれも採用OKということになります。
まとめ
巷では、個人事業者の場合は「① 契約上の支払日に計上する方法」「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」のいずれも採用してOK、法人の場合は「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」しか認められないとする言説がありますが、その考えは誤りです。
国税庁が公表している法令解釈通達において、法人税法上、使用料等を支払日の属する事業年度に益金算入することが認められると明記されているため、法人であっても「① 契約上の支払日に計上する方法」「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」のいずれも採用することができます。
消費税法における資産の譲渡等の時期も、不動産等の貸主が個人事業者であるか法人であるかに関係なく、「① 契約上の支払日に計上する方法」「② 実際の貸付期間に対応させて計上する方法」のいずれも採用OKということになります。



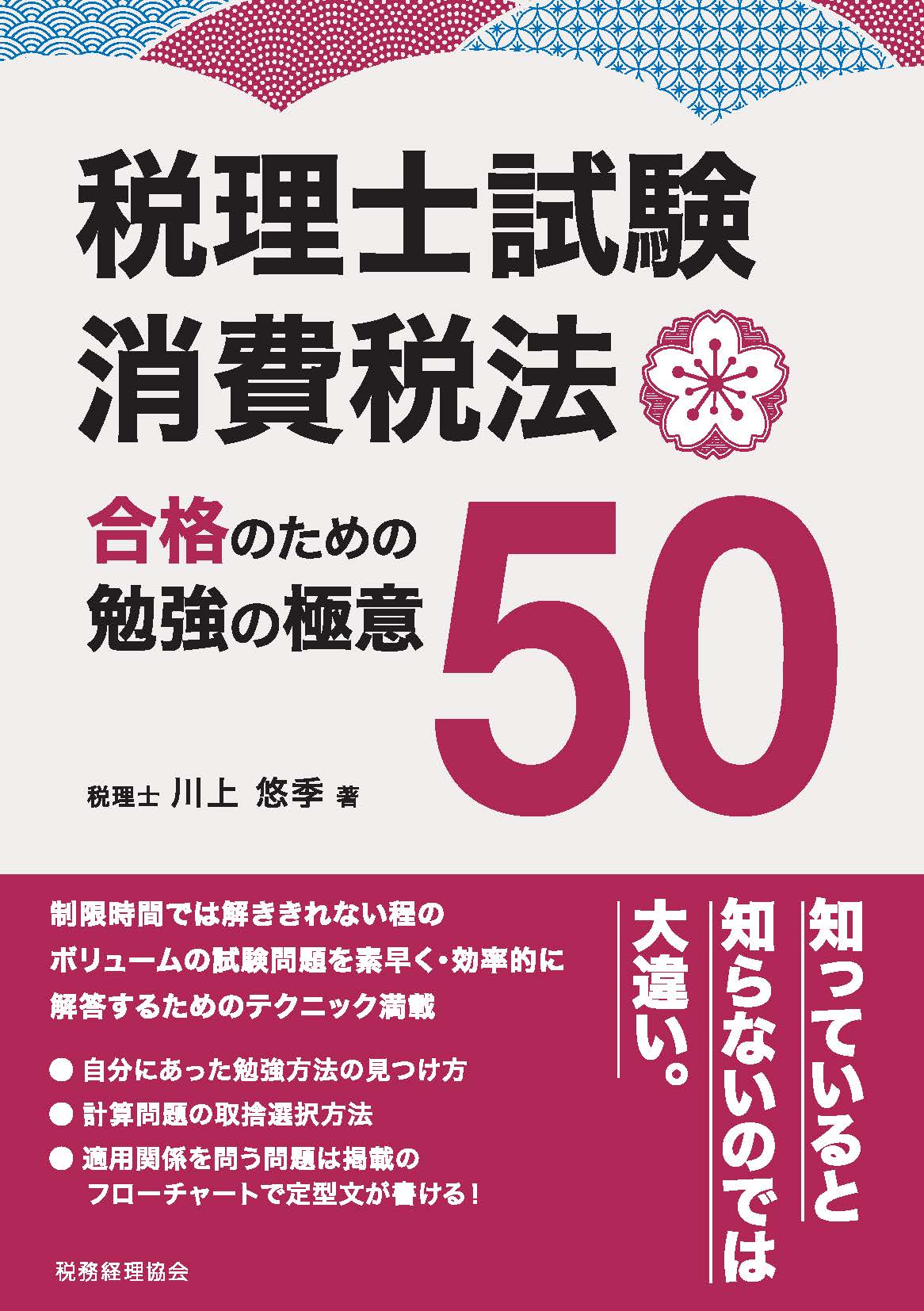











-端っこカット小-1.jpg)
はじっこカット小-1.jpg)
-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)
-端っこカット小.jpg)
はじっこカット.jpg)
-はじっこカット小.jpg)


