-e1659443507464.png)
第72回(令和4年度=2022年度)の税理士試験消費税法の解答速報を作成しました!
今回は前編[第一問]の理論問題について解説します!
後編の[第二問]の計算問題の解説が見たい方は次の記事をご覧ください。
はじめに
この解答速報は、消費税法一問一答アプリシリーズ制作者である私が個人的に制作したものです。
私が教材制作者として所属している資格学校の見解ではありません。
また、去年と同様に予防線を張りますが、この解答速報は徹夜ですべて一人で制作しています。集中力が落ちていたり問題条件の読み飛ばし等で間違った解答を書いている箇所があるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。(疑問のある箇所がある場合はお問合せフォームまたはTwitterでご連絡ください。生活リズムが不規則なのでお返事は遅くなることがあります。)
文章は基本的に音声認識ソフトを使って文字起こしをしています。注意してはいますが、急いで書いているため、誤字・脱字が含まれている可能性があることをご了承ください。(誤字・脱字は発見次第適宜修正していきます。)
なお、今年は予想配点はつけません。
問1
問1 次の⑴及び⑵の問に答えなさい。
⑴ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税の控除に関して、「特定課税仕入れ」の意義、「特定課税仕入れに係る対価の返還等」の意義及び「特定課税仕入れに係る支払対価の額」の意義を述べた上で、当該消費税額の控除に係る内容と要件を述べなさい。また、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除で、相続、合併又は分割があった場合の取扱いについて述べなさい。なお、解答に当たって、消費税法施行令に定める事項について触れる必要はない。
【解答】
⑴ 特定課税仕入れの意義
特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(注1)を受けること(注2)をいう。
(注1)所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
(注2)他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)に該当することとなるものに限る。
特定仕入れとは、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
特定資産の譲渡等とは、事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質又は取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
電気通信利用役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介するものを除く。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われるもの以外のものをいう。
特定役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(注3)をいう。
(注3)電気通信利用役務の提供を除く。
⑵ 特定課税仕入れに係る対価の返還等の意義
特定課税仕入れに係る対価の返還等とは、国内において行った特定課税仕入れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金等の全部若しくは一部の減額をいう。
⑶ 特定課税仕入れに係る支払対価の額の意義
特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額をいう。)をいう。
⑷ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税の控除の内容
① 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った特定課税仕入れにつき、値引きまたは割戻しを受けたことにより、特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注4)の合計額を控除する。
(注4)返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の7.8を乗じて算出した金額
② 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った課税仕入または特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引きもしくは割戻しを受けたことにより、仕入れに係る対価の返還等(注5)を受けた場合には、一定の金額をその返還等を受けた日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(注5)仕入れに係る対価の返還等とは、国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額又は特定課税仕入れに係る支払対価の額の全額若しくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金等の全部若しくは一部の減額をいう。
⑸ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税の控除を受けるための要件
上記⑷の規定は、特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。
⑹ 相続、合併又は分割があった場合の取扱い
① 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
相続により事業を承継した相続人が、被相続人により行われた特定課税仕入れにつき特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った特定課税仕入れにつき特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、この規定を適用する。
この規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
② 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
相続により事業を承継した相続人が、被相続人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、この規定を適用する。
この規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
⑵ 消費税法上の「価格の表示」について、義務付けられる対象者、対象となる取引及び対象から除かれている取引に触れながらその内容を述べ、それを踏まえて次のイ~ニの価格が、当該「価格の表示」の対象となるかどうかを答えなさい。なお、解答に当たって、価格の具体的な表示例に触れる必要はない。
イ スーパーマーケットのチラシに表示する価格
ロ 卸売業者が小売店向けに作成した業務用商品カタログに表示する価格
ハ 見積書に表示する価格
ニ 口頭で伝える価格
【解答】
⑴ 内容
事業者(免除事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
⑵ 判定
イ スーパーマーケットのチラシに表示する価格
[判定]対象となる。
[理由]不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に該当するため、「価格の表示」について、総額表示が義務付けられる対象となる。
ロ 卸売業者が小売店向けに作成した業務用商品カタログに表示する価格
[判定]対象とならない。
[理由]専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合に該当するため、「価格の表示」について、総額表示が義務付けられる対象とならない。
ハ 見積書に表示する価格
[判定]対象とならない。
[理由]総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としているため、見積書については、総額表示義務の対象とはならない。
ニ 口頭で伝える価格
[判定]対象とならない。
[理由]総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となる。事業者があらかじめ消費者に対して行う価格の表示とは、店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告などの表示媒体により行われるものをいい、口頭で伝えるような価格は総額表示義務の対象とならない。
(価格の表示)
第六十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
総額表示義務のない場合
Q 見積書、契約書、請求書等は、消費税額を含めた総額表示の対象となりますか。A 総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。(消法63)
概要
総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものです。総額表示義務の対象
総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となります。したがって、価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません。また、口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません。
(注)事業者があらかじめ消費者に対して行う価格の表示であれば、それがどのような表示媒体(店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など)により行われるものであるかを問いません。
問2
問2 日本国内に本店を有する株式会社A(以下「A社」という。)の次の⑴~⑸の取引に関する消費税法令上の適用関係について、その理由を示して簡潔に答えなさい。
⑴ A社は、日本国内に本店を有する株式会社B(以下「B社」という。)のインドネシア共和国に所在する工場から商品を仕入れ、これを日本国内に持ち込まないで直接マレーシアの発注者である外国法人Cに納品している。なお、この取引については、A社の本店で仕入れ・売上げを計上しており、また、A社とB社との間の売買は、国内において、B社の本店から託送中の商品に係る船荷証券の譲渡を受けて、商品代金を支払っている。
【解答】
(判定)不課税取引
(理由)
船荷証券の譲渡は、当該船荷証券に表彰されている貨物の譲渡であるから、原則として当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所により国内取引に該当するかどうかを判定する。なお、その船荷証券に表示されている荷揚地が国内である場合の当該船荷証券の譲渡については、その写しの保存を要件として国内取引に該当するものとして取り扱って差し支えないこととされている。
本問においては、商品を日本国内に持ち込まずに外国法人Cに納品しており、また、B社の本店から託送中の商品に係る船荷証券の譲渡を受けていることから、当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所は国外であり、かつ、荷揚地も国外であるため、国内取引に該当せず、不課税取引となる。
(船荷証券の譲渡に係る内外判定)
5-7-11 船荷証券の譲渡は、当該船荷証券に表彰されている貨物の譲渡であるから、原則として当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所により国内取引に該当するかどうかを判定するのであるが、その船荷証券に表示されている「荷揚地」(PORT OF DISCHARGE)が国内である場合の当該船荷証券の譲渡については、その写しの保存を要件として国内取引に該当するものとして取り扱って差し支えない。
なお、本邦からの輸出貨物に係る船荷証券の譲渡は、当該貨物の荷揚地が国外であることから、国外取引に該当する。
⑵ A社が製造する製品αの特許権は、アメリカ合衆国およびフランス共和国の二国のみで登録されている。A社は、アメリカ合衆国の外国法人Dに対し、同国で登録された特許権を譲渡し、その対価を収受した。
【解答】
(判定)免税取引
(理由)
特許権が2以上の国で登録されている場合は、権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地で国内判定を行う。
本問の場合、権利の譲渡を行う者(A社)の住所地が国内にあるため国内取引に該当し、非居住者に対する無形固定資産の譲渡であるため免税取引に該当する。
⑶ A社は、A社の出資先である外国法人E(以下「E社」という。)の株式を国内に本店を有する株式会社Fに譲渡し、その対価を収受した。なお、E社は株券を発行していないためA社はその株券を有しておらず、また、E社の株式については振替機関等が取り扱うものではない。
【解答】
(判定)不課税取引
(理由)
株券の発行がない株式の譲渡は、有価証券に類するものの譲渡として、振替機関等が取り扱うものについては、当該振替機関等の所在地により判定し、振替機関等が取り扱わないものについては、当該権利を発行した法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定する。
E社の株式は振替機関等が取り扱うものではないため、E社の株式を発行した法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定する。
したがって、E社の本店は国外に所在することから、E社の株式の譲渡は国内取引に該当せず、不課税取引となる。
| 有価証券の種類 | 内外判定基準 | |
| 振替機関等が取り扱うもの | 振替機関等の所在地 | |
| 振替機関等が取り扱わないもの | 券面あり | 有価証券の所在地 |
| 券面なし | 権利又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地 | |
⑷ A社は、シンガポール共和国の外国法人G(以下「G社」という。)に対して現地通貨で金銭を貸し付けている。A社は、貸付金に係る利息をG社から収受し、A社の本店で受取利息として計上している。
【解答】
(判定)非課税取引
(理由)
金銭の貸付け等に係る国内取引の判定は、貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行う。
本問の場合、A社の本店で受取利息として計上していることから貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地が国内であると判断できるため、国内取引に該当する。
また、利子を対価とする金銭の貸付け等に該当するため、非課税取引に該当する。
さらに、利子を対価とする金銭の貸付け等でその債務者が非居住者である者に該当するため、非課税資産の輸出に該当する。
したがって、当該受取利息は、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。
⑸ A社は、アメリカ合衆国に本店を有し書籍の販売業を営む外国法人H(以下「H社」という。)から、インターネットを介して事業者向けの専門誌(電子書籍)の配信を受け購入した。なお、H社はこれまで、日本の税務に係る申請手続を行ったことはない。
【解答】
(判定)処理なし(回答用紙が手に入らないため選択肢がどういう風になっていたかわかりませんが、課税仕入れにはならない・仕入税額控除不可という旨の解答です。)
(理由)
インターネットを介した事業者向けの専門誌(電子書籍)の配信は、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものには該当しないため、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する。
国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合は、当分の間、その消費者向け電気通信利用役務の提供はなかったものとされるため、仕入税額控除を受けることはできないこととされているが、その消費者向け電気通信利用役務の提供を行った国外事業者が「登録国外事業者」に該当する場合は、仕入税額控除を受けることが認められる。
登録国外事業者とは、次に掲げる要件を満たす一定の国外事業者(免税事業者を除く。)として、納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に申請書を提出し、国税庁長官の登録を受けた事業者をいう。
① 国内において行う電気通信利用役務の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が国内にあること又は消費税に関する税務代理人(国税通則法に規定する税務代理人をいう。)があること。
② 国税の滞納がないこと及び登録国外事業者の登録取消しから1年を経過していること。
H社はこれまで、日本の税務に係る申請手続を行ったことはないことから、上記要件を満たしていないと判断されるため、登録国外事業者には該当しない。
したがって、H社から受けたインターネットを介した事業者向けの専門誌(電子書籍)の配信は、登録国外事業者に該当しない国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供であり、その消費者向け電気通信利用役務の提供はなかったものとされるため、仕入税額控除を受けることはできない。
第一問(理論問題)の総評
今年の第一問・理論問題はここ数年の理論問題の中では最も難易度の高い問題だったと感じました。(感想はあくまでも個人的な主観ですのでご了承ください。)
例年であればもう少し得点しやすい基本的な内容の問題もチラホラ入っているものなんですが、今年は得点しやすい基本的な問題といえる問題は、問1⑴の意義と問2⑷のG社への金銭貸付けくらいしかないんじゃないでしょうか・・・。
今回の理論問題はそこそこ実力がある人でも、手こずって点がなかなか取れなかったのではないかと思います。
合格ボーダーはおそらくかなり低くなると思われますので、あまり自信がなかった人でも、取るべきところがしっかり取れていれば大丈夫だと思います。
それでは、第二問計算編も完成し次第また後ほど投稿したいと思います。
(もし誤字・脱字・勘違い等によるミスがあったらTwitterやメールなどで優しく教えてください。。。)
(追記)受験生の感想
僕個人の感想としては、今回の理論問題はかなり難しかったと思ったのですが、Twitterなどを通じて受験生の感想を聞いた限り「そこまで言うのは大げさやろ」というような感じでした。
僕自身が受験生だったのはもう7年も前になるため現役受験生の感覚と若干乖離していたのかもしれません。
僕が聞いた限りの受験生の方の感想は本当に十人十色で、「手も足も出ないほど難しかった」という方から、「ちょっと難しいくらいかな」「取捨選択さえしっかりできていればむしろ簡単」という方までいらっしゃり、今回の試験は良くも悪くも、ふるいにかけてしっかりと実力を試すのに最適な問題だったといえるのかもしれません。
今回の理論問題については、全体的には「やや難しい」くらいの評価が一番妥当なんじゃないかという感じでした。
第二問(計算問題編)の解答速報記事は以下となります。
あと、本試験とは関係ないですがこの場を借りて他の記事の宣伝をさせてください。
まず、先日、第45回日税研究賞受賞者として、第66回日税連定期総会にお呼ばれし、めちゃくちゃ楽しい()経験をしてきたのでよかったら体験記↓を読んでください!
また、入選した論文「現物出資が行われた場合の消費税の課税標準に関する一考察」の内容は、次の記事で詳しく解説しています。この論文で提案した内容を、本当の税制改正案として実現させたいと思っているので、興味がありましたら是非ご一読ください!

-e1659449822687-150x150.png)





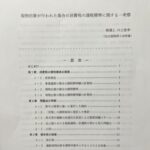













-端っこカット小-1.jpg)
はじっこカット小-1.jpg)
-はじっこカット小-1.jpg)

はじっこカット小.jpg)
-端っこカット小.jpg)
はじっこカット.jpg)
-はじっこカット小.jpg)


